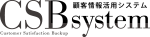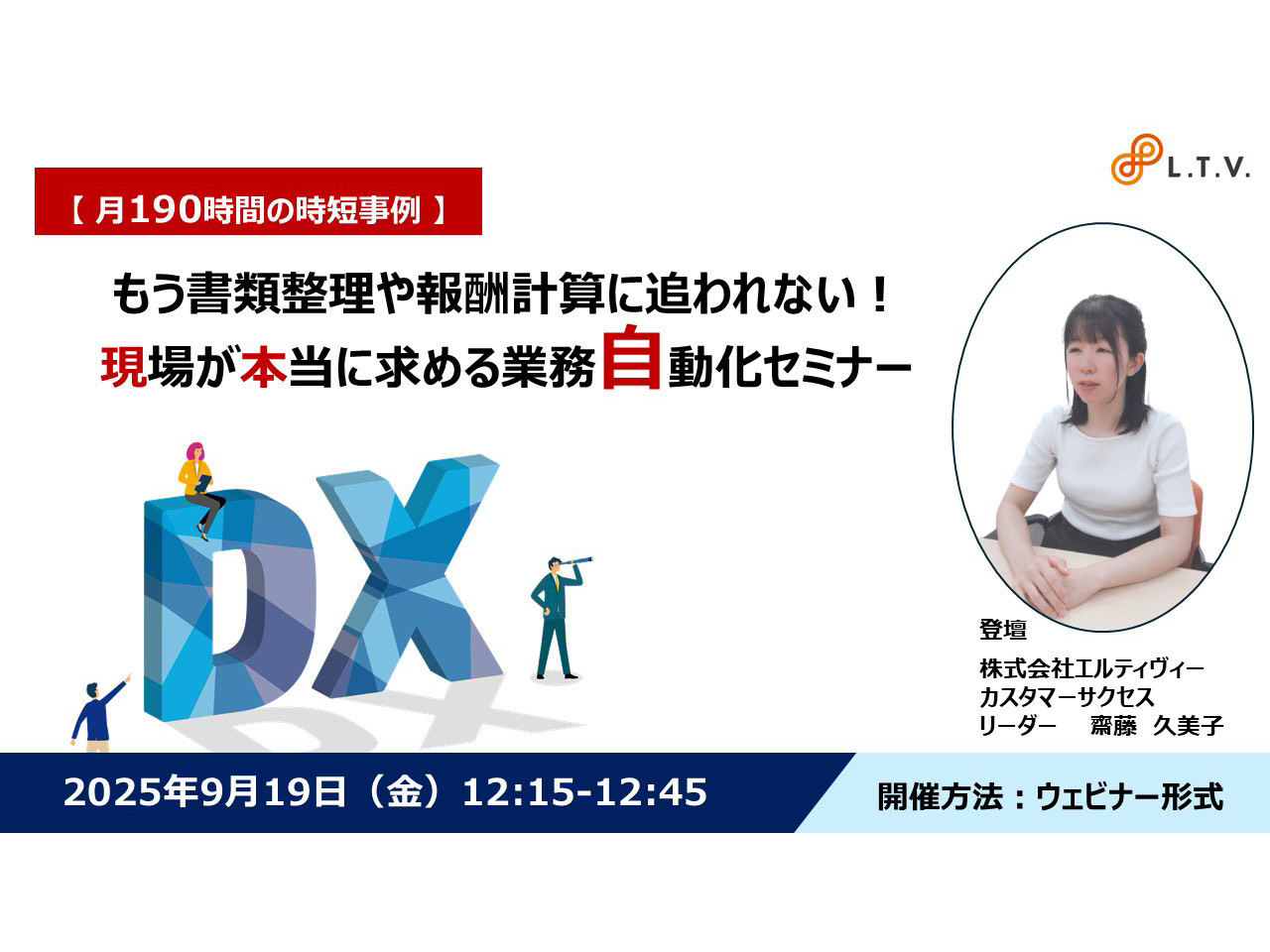【プチ解説】「保険会社向けの総合的な監督指針」の改正案
2025.05.19

損保業界で起きた一連の不祥事を受けて、見直されることになった保険会社向けの監督指針。2025年5月12日にその改正案(一部)が公表されました。本コラムでは、その改正内容の一部をピックアップし、弊社の見解などを交えてお伝えします。
「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)
(6/13までパブリックコメント募集中)
現在はパブリックコメント募集中で正式な改正ははまだ先で、今後第2弾の指針案も公表される見込みです。現時点での読み解き内容ですのでご了承ください。
目次
改正の背景・経緯
旧ビッグモーター問題や損害保険会社4社によるカルテル事案、個人情報の漏えい問題など損保業界で起きた不祥事を受け、金融庁が取り決めている「保険会社向けの総合的な監督指針」が一部改正されることになりました。今回の改正は、先述の通り、主に損害保険業界での問題を受けた内容となっています。
改正のポイントは以下の通りです。
・損害保険会社による保険代理店に対する指導等の実効性の確保
・保険代理店等に対する過度な便宜供与の防止
・保険代理店等に対する不適切な出向の防止
・代理店手数料の算出方法適正化
・顧客等に関する情報管理態勢の整備
・政策保有株式の縮減
・仲立人の媒介手数料の受領方法の見直し
なお、金融庁のホームページには「上記以外の有識者会議の報告書で提言された内容や、ワーキング・グループの報告書の内容等を踏まえた監督指針の更なる改正については、引き続き、検討を行っていく予定です。」とあります。
第2弾の改正案も公表されると見られ、その際は今回の改正案には盛り込まれなかった「保険乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保」についても言及されるのではないかと言われているようです。
損害保険会社による保険代理店に対する指導等の実効性の確保
【II―4―2―1 適正な保険募集管理態勢の確立】
(4)・・・文言追加
特定保険募集人等(特定保険募集人及び損害保険会社の保険募集を専ら行う従業員をいう。Ⅱ-4-2-1(4)において同じ)の教育・管理・指導 また、保険会社においては、営業面への影響の大きさにかかわらず、保険代理店における体制整備や保険募集等の適切性について、日常的な教育・管理・指導に加え、代理店監査等を通じて検証し、課題等が認められた場合には期限を定めて改善を求めるなど、保険代理店に対する指導等が適切に行われるよう、その実効性を十分に確保しているか。
(4)ウ.・・・文言追加
監査等の手法として、代理店による自己点検のみに依拠することなく、無予告での訪問による監査等を実施できる態勢を整備しているか。
(5)・・・新設
監督手法・対応 保険会社による特定保険募集人に対する指導等の状況については、保険会社に対する深度あるヒアリング等のオフサイトモニタリングを行うことや、必要に応じて法第128条に基づく報告を求めること、法第129条に基づく立入検査の実施を通じて把握することとする。その上で、重大な問題があると認められる場合には、法第132条に基づき行政処分を行うものとする。
(4)・・・文言追加
特定保険募集人等(特定保険募集人及び損害保険会社の保険募集を専ら行う従業員をいう。Ⅱ-4-2-1(4)において同じ)の教育・管理・指導 また、保険会社においては、営業面への影響の大きさにかかわらず、保険代理店における体制整備や保険募集等の適切性について、日常的な教育・管理・指導に加え、代理店監査等を通じて検証し、課題等が認められた場合には期限を定めて改善を求めるなど、保険代理店に対する指導等が適切に行われるよう、その実効性を十分に確保しているか。
(4)ウ.・・・文言追加
監査等の手法として、代理店による自己点検のみに依拠することなく、無予告での訪問による監査等を実施できる態勢を整備しているか。
(5)・・・新設
監督手法・対応 保険会社による特定保険募集人に対する指導等の状況については、保険会社に対する深度あるヒアリング等のオフサイトモニタリングを行うことや、必要に応じて法第128条に基づく報告を求めること、法第129条に基づく立入検査の実施を通じて把握することとする。その上で、重大な問題があると認められる場合には、法第132条に基づき行政処分を行うものとする。
(4)で追記された「営業面への影響の大きさにかかわらず」とは、規模の大きい代理店に対する忖度を踏まえた文言追加と思われます。
また、(4)③ウと(5)では、「代理店は自己点検のみに依拠することなく」「深度あるヒアリング」とあり、監査や点検の形骸化を防ぐことが求められています。
保険代理店等に対する過度な便宜供与の防止
【Ⅱ-4-2-9 保険募集人の体制整備義務(法第 294 条の 3 関係) 】
(6)・・・新設
二以上の所属保険会社等を有する保険募集人が、保険会社等に対して過度の便宜供与を求めることは、当該保険募集人において、便宜供与の実績に応じて特定の保険商品を推奨する事態を誘発し、顧客の適切な商品選択の機会を阻害するおそれがあるため、防止される必要がある。 そこで、二以上の所属保険会社等を有する保険募集人は、比較推奨販売を行う場合には、顧客の適切な商品選択の機会を確保する観点から、Ⅱ-4-2-12を踏まえ、保険会社等に対し過度の便宜供与を求めること及び保険会社等から過度の便宜供与を受け入れることを防止するため、自己の規模や特性に応じて、以下の措置を講じているか。
ア. 過度の便宜供与に係る判断基準の社内規則等への規定
イ. 上記ア.の社内規則等を踏まえた、保険募集人による保険会社等に対する便宜供与の要求及び受入れの制限に関する適切な教育・管理・指導の実施
ウ. 保険会社等からの便宜供与による自社の比較推奨販売への影響の有無に係る確認・検証
エ. 上記ウ.の確認・検証結果を踏まえた、経営陣における評価・対応の検討
オ. 自社の比較推奨販売への影響が生じていると認められる場合における、適切な解消措置の実施及び改善に向けた態勢整備
(6)・・・新設
二以上の所属保険会社等を有する保険募集人が、保険会社等に対して過度の便宜供与を求めることは、当該保険募集人において、便宜供与の実績に応じて特定の保険商品を推奨する事態を誘発し、顧客の適切な商品選択の機会を阻害するおそれがあるため、防止される必要がある。 そこで、二以上の所属保険会社等を有する保険募集人は、比較推奨販売を行う場合には、顧客の適切な商品選択の機会を確保する観点から、Ⅱ-4-2-12を踏まえ、保険会社等に対し過度の便宜供与を求めること及び保険会社等から過度の便宜供与を受け入れることを防止するため、自己の規模や特性に応じて、以下の措置を講じているか。
ア. 過度の便宜供与に係る判断基準の社内規則等への規定
イ. 上記ア.の社内規則等を踏まえた、保険募集人による保険会社等に対する便宜供与の要求及び受入れの制限に関する適切な教育・管理・指導の実施
ウ. 保険会社等からの便宜供与による自社の比較推奨販売への影響の有無に係る確認・検証
エ. 上記ウ.の確認・検証結果を踏まえた、経営陣における評価・対応の検討
オ. 自社の比較推奨販売への影響が生じていると認められる場合における、適切な解消措置の実施及び改善に向けた態勢整備
「比較推奨販売」が明文化され、適切な比較推奨販売を行うための具体的な措置が(6)に記載されました。保険乗合代理店には、「(6)ア.過度の便宜供与に係る判断基準の社内規則等への規定」が求められた上で、そのための社員教育や体制整備も必要となってきます。
【Ⅱ-4-2-12 保険代理店等に対する便宜供与 】・・・新設(一部抜粋)
(1) 過度の便宜供与の防止
② 過度の便宜供与に係る判断基準
保険会社が保険代理店等に対して行う便宜供与に関し、過度なものであるか否かについては、以下に基づき判断する。
ア.自社の保険商品の優先的な取扱いを誘引する便宜供与 保険代理店等に対する便宜供与のうち、以下のいずれかの要素を含むものについては、特に顧客の適切な商品選択の機会を阻害するおそれが高いことから、過度の便宜供与に該当する。
(ア) 便宜供与の実績に応じて、当該保険代理店や保険募集人である保険代理店の役員又は使用人において保険契約数や保険引受シェアの調整が行われる場合
(イ) 保険代理店等から保険会社に対し、物品等の販売数量の目標設定や購入数量の割当て等が行われる場合
イ.実質的に自社の保険商品の優先的な取扱いを誘引するもの 上記ア.のほか、保険代理店等に対する便宜供与が過度なものであるか否かについては、当該便宜供与の趣旨・目的のほか、価格・数量・頻度・期間及びその負担者等を総合的に勘案しつつ、当該便宜供与によって生じ得る弊害の内容・程度を考慮し、社会通念に照らして妥当であるかによって判断する。 なお、判断は個別具体的に行われるべきであるが、例えば、以下の行為については、実質的に自社の保険商品の優先的な取扱いを誘引するものとして、過度の便宜供与に該当し得る。
(ア) 保険会社の役職員が、保険代理店等から、他の保険会社の購入実績との比較を提示されるなど黙示の圧力を受けたことを背景として、自社の役職員に対し、数量等の報告やとりまとめを伴う物品の購入をあっせんする行為
(イ) 保険代理店等が主催するイベント等において、保険会社の役職員等が保険業と関連性の低い役務を提供する形で参加・協力する行為
(ウ) 保険代理店等が主催するイベント等において、保険会社の役職員等が休日や業務時間外に参加・協力する行為
(エ) 本来は保険代理店等が負担すべき費用を保険会社が負担する行為、又は保険代理店等が自らの責任において行うべき業務に対し保険会社が役務を提供する行為
(オ) 保険代理店等の求めに応じ、役務の対価としての実態がない又は保険会社若しくは保険代理店等において対価性の検証が困難な業務委託費、協賛金、商標使用料、広告費用等の金銭を拠出する行為
(1) 過度の便宜供与の防止
② 過度の便宜供与に係る判断基準
保険会社が保険代理店等に対して行う便宜供与に関し、過度なものであるか否かについては、以下に基づき判断する。
ア.自社の保険商品の優先的な取扱いを誘引する便宜供与 保険代理店等に対する便宜供与のうち、以下のいずれかの要素を含むものについては、特に顧客の適切な商品選択の機会を阻害するおそれが高いことから、過度の便宜供与に該当する。
(ア) 便宜供与の実績に応じて、当該保険代理店や保険募集人である保険代理店の役員又は使用人において保険契約数や保険引受シェアの調整が行われる場合
(イ) 保険代理店等から保険会社に対し、物品等の販売数量の目標設定や購入数量の割当て等が行われる場合
イ.実質的に自社の保険商品の優先的な取扱いを誘引するもの 上記ア.のほか、保険代理店等に対する便宜供与が過度なものであるか否かについては、当該便宜供与の趣旨・目的のほか、価格・数量・頻度・期間及びその負担者等を総合的に勘案しつつ、当該便宜供与によって生じ得る弊害の内容・程度を考慮し、社会通念に照らして妥当であるかによって判断する。 なお、判断は個別具体的に行われるべきであるが、例えば、以下の行為については、実質的に自社の保険商品の優先的な取扱いを誘引するものとして、過度の便宜供与に該当し得る。
(ア) 保険会社の役職員が、保険代理店等から、他の保険会社の購入実績との比較を提示されるなど黙示の圧力を受けたことを背景として、自社の役職員に対し、数量等の報告やとりまとめを伴う物品の購入をあっせんする行為
(イ) 保険代理店等が主催するイベント等において、保険会社の役職員等が保険業と関連性の低い役務を提供する形で参加・協力する行為
(ウ) 保険代理店等が主催するイベント等において、保険会社の役職員等が休日や業務時間外に参加・協力する行為
(エ) 本来は保険代理店等が負担すべき費用を保険会社が負担する行為、又は保険代理店等が自らの責任において行うべき業務に対し保険会社が役務を提供する行為
(オ) 保険代理店等の求めに応じ、役務の対価としての実態がない又は保険会社若しくは保険代理店等において対価性の検証が困難な業務委託費、協賛金、商標使用料、広告費用等の金銭を拠出する行為
ここでは「過度の便宜供与に係る判断基準」の事例がかなり具体的に明文化されました。実際にこれまで不祥事として問題になった点に直接言及するようなものもあり、金融庁の強い意向が感じ取れるところです。
保険代理店等に対する不適切な出向の防止
【Ⅱ-4-2-13 保険代理店に対する出向 】・・・新設(一部抜粋)
(3) 出向の適切性に係る留意事項
① 当該出向が、以下の点に照らし、顧客の適切な商品選択の機会を阻害するものではないか。
ア. 特定の保険代理店への出向が、当該保険代理店における出向元保険会社のシェアの拡大等の営業推進として機能するなど、出向元の保険商品の優先的な取扱いを誘引するおそれを有するものではないか。
イ. 保険募集に直接関与するなど、出向先において従事する業務の内容が、出向元の保険商品の優先的な取扱いを誘引するおそれを有するものではないか。
② 出向先の保険代理店において、出向者が顧客等の同意なく当該保険代理店の顧客情報等を出向元の保険会社に共有するおそれが生じないことを確保しているか。
③ 当該出向が、出向者数や出向期間、出向先での業務内容、当該代理店の規模や特性等に照らし、出向先保険代理店の自立を阻害するものではないか。
④ 保険金関連事業を兼業する保険代理店に対する出向であって、修理費の算出等の保険金請求に関わる部門の業務に従事する場合など、当該出向が、保険会社における利益相反管理の観点から不適切なものではないか。
(3) 出向の適切性に係る留意事項
① 当該出向が、以下の点に照らし、顧客の適切な商品選択の機会を阻害するものではないか。
ア. 特定の保険代理店への出向が、当該保険代理店における出向元保険会社のシェアの拡大等の営業推進として機能するなど、出向元の保険商品の優先的な取扱いを誘引するおそれを有するものではないか。
イ. 保険募集に直接関与するなど、出向先において従事する業務の内容が、出向元の保険商品の優先的な取扱いを誘引するおそれを有するものではないか。
② 出向先の保険代理店において、出向者が顧客等の同意なく当該保険代理店の顧客情報等を出向元の保険会社に共有するおそれが生じないことを確保しているか。
③ 当該出向が、出向者数や出向期間、出向先での業務内容、当該代理店の規模や特性等に照らし、出向先保険代理店の自立を阻害するものではないか。
④ 保険金関連事業を兼業する保険代理店に対する出向であって、修理費の算出等の保険金請求に関わる部門の業務に従事する場合など、当該出向が、保険会社における利益相反管理の観点から不適切なものではないか。
出向自体は、多くの企業が行っている事であっても保険業界ならではの観点での留意事項が具体化されました。
①保険会社役職員の出向により、出向元の保険商品が優先的に取り扱われる恐れ
②出向者が保険代理店の顧客情報を出向元に不適切に共有する恐れ
③出向が保険代理店の自立を阻害する恐れ
④保険金請求関連部門に出向がする場合に、出向元である保険会社との利益相反にあたる恐れ
こちらも、実際の不祥事案を受けての改正と言う印象が強くみられるものでした。
顧客等に関する情報管理態勢の整備
【Ⅱ-4-5 顧客等に関する情報管理態勢 Ⅱ-4-5-2 主な着眼点】・・・文言追加
③ 顧客等に関する情報へのアクセス管理の徹底(アクセス権限を有する者の範囲がNeed to Know原則を逸脱したものとなることやアクセス権限を付与された本人以外が使用することの防止等)、内部関係者による顧客等に関する情報の持出しの防止に係る対策、外部からの不正アクセスの防御等情報管理システムの堅牢化などの対策を含め、顧客等に関する情報を適切に管理するための態勢が構築されており、コンプライアンス部門の関与のもと当該顧客等に関する情報の管理状況を適時・適切に検証できる体制となっているか。
③ 顧客等に関する情報へのアクセス管理の徹底(アクセス権限を有する者の範囲がNeed to Know原則を逸脱したものとなることやアクセス権限を付与された本人以外が使用することの防止等)、内部関係者による顧客等に関する情報の持出しの防止に係る対策、外部からの不正アクセスの防御等情報管理システムの堅牢化などの対策を含め、顧客等に関する情報を適切に管理するための態勢が構築されており、コンプライアンス部門の関与のもと当該顧客等に関する情報の管理状況を適時・適切に検証できる体制となっているか。
情報漏えい対策で基本とされる、「情報が必要な人のみアクセスできるようにし、不要な人がアクセスできないようにする」「必要最小限」と言う考え方である、「Need to Know原則」が追記されました。
金融商品取扱業者や銀行向けの監督指針にはすでに盛り込まれており、保険会社向けの監督指針もそれらに追随する形となりました。
政策保有株式の縮減
【Ⅱ-4-12 政策保有株式の縮減】・・・新設(一部抜粋)
(1)意義 損害保険業界においては、企業向け保険契約の入札等において、いわゆる政策保有株式等の実績が少なからずシェアに影響を及ぼしており、適正な競争を阻害していた。その結果、保険商品や保険サービス自体で適正に競争を行うよりも、保険料水準やシェアを維持するため、競争を避け、事前に保険料等を調整するといった不適切事案が発生し、業界に対する信頼が大きく損なわれた事例が認められている。このように、保険市場においては、政策保有株式が公正な競争を阻害する要因となり得ることを踏まえ、保険会社は以下の点を重視して、コンプライアンス上問題となり得る行為を防止する態勢を構築すべきである。
なお、政策保有株式のほか、保険シェアを獲得することを意図した預金協力や融資も、政策保有株式と同様に、公正な競争を阻害する要因となり得ることにも留意する。
(1)意義 損害保険業界においては、企業向け保険契約の入札等において、いわゆる政策保有株式等の実績が少なからずシェアに影響を及ぼしており、適正な競争を阻害していた。その結果、保険商品や保険サービス自体で適正に競争を行うよりも、保険料水準やシェアを維持するため、競争を避け、事前に保険料等を調整するといった不適切事案が発生し、業界に対する信頼が大きく損なわれた事例が認められている。このように、保険市場においては、政策保有株式が公正な競争を阻害する要因となり得ることを踏まえ、保険会社は以下の点を重視して、コンプライアンス上問題となり得る行為を防止する態勢を構築すべきである。
なお、政策保有株式のほか、保険シェアを獲得することを意図した預金協力や融資も、政策保有株式と同様に、公正な競争を阻害する要因となり得ることにも留意する。
政策保有株が、適正な競争を阻害し得ることを損害保険業界におけるカルテル問題に触れながら明言し、保険会社に適正化を求めています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いかがでしたでしょうか?
今回の指針の改正案は、OKなこと・NGなことが割と具体的に追記された、という印象をお持ちの方も多いかと思います。第2弾の改正案も公表されると見られていますので、引き続き弊社も注視してまいります。
エルティヴィーのコラムでは、今後も業界の最新情報やCSBの活用方法をお伝えしています。
その他、関連コラムはこちらからご覧いただけます↓
いまさら聞けない?代理店業務品質評価運営とは(事例付き)

お気軽にご相談ください。
エルティヴィーでは保険代理店さまの体制整備から、顧客管理、マーケティングまでトータルで支援しています。
CSBに関するお問合せやご質問などございましたらご相談ください。
03-6234-6392
(受付時間 平日: 9:00〜17:30)